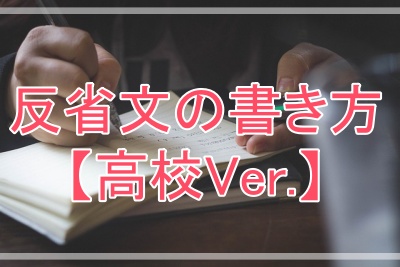「やらかした…」
そんな時に高校から「反省文を書くように」言われますよね?
今回の記事では「高校の反省文をスマホを使って書くときのポイントや例文」をまとめています!
ぜひ最後までご覧ください。
高校生が反省文を書くときの基本構成
反省文には一般的に以下の構成を取り入れると良いです。
1. 反省文の書き出し:事実や状況の説明
反省文の冒頭では、何が起きたのか、どのような行動が問題だったのかを具体的に記述します。
例えば、「○月○日の授業中にスマートフォンを使用し、授業の妨げとなってしまいました」など。
ポイントは、事実を簡潔に述べることです。
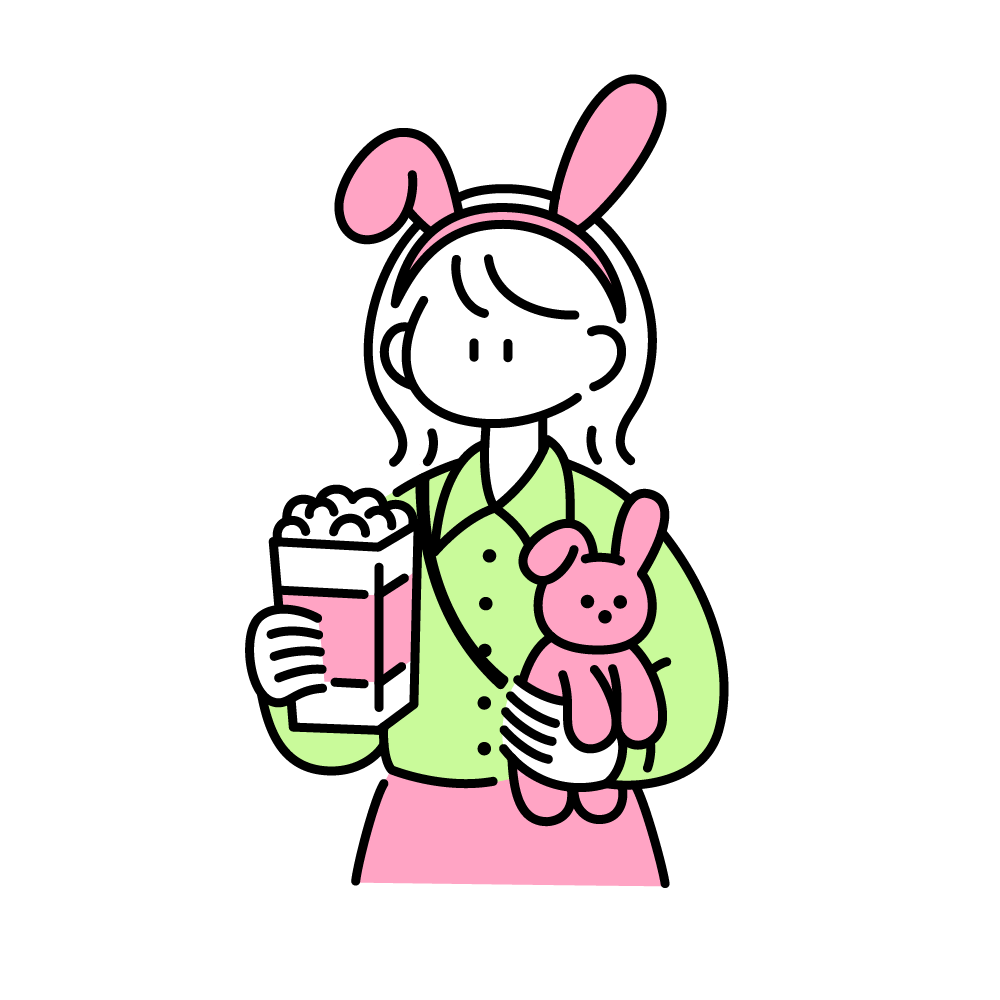
最初に簡潔に事実を述べます
2. その行動の問題点と自己の反省
次に、自分の行動がどのように問題だったのかを具体的にし、それを言葉にします。
例えば「授業中のスマートフォン使用は、教師やクラスメートに迷惑をかける行為でした」など。
自分がどのような影響を与えたのかを具体的に書くことで、反省の深さを伝えられます。
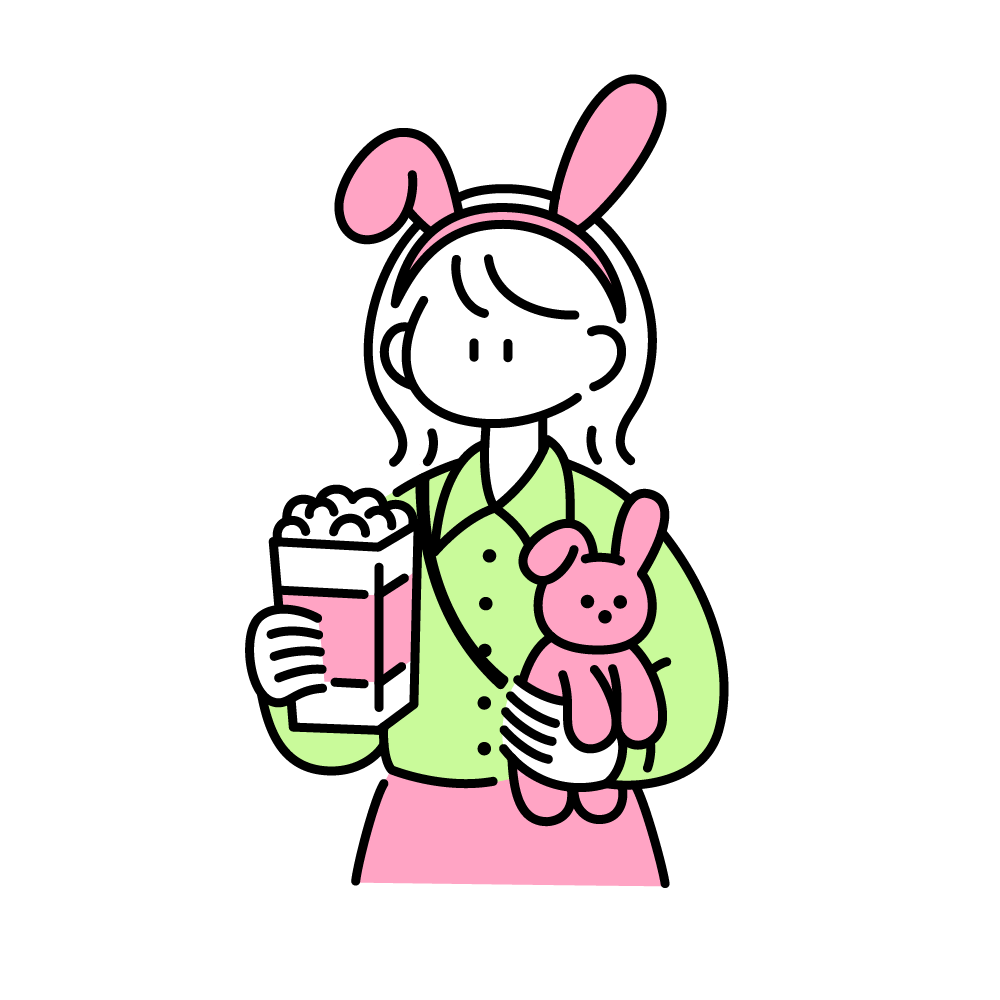
借りた言葉ではなく状況に応じて具体的に
3. 今後の改善策
最後に、同じミスを繰り返さないための具体的な改善策を示します。
例えば、「今後はスマートフォンをロッカーにしまい、授業中は一切使用しません」など。
実現可能な行動を示すことが信頼につながります。
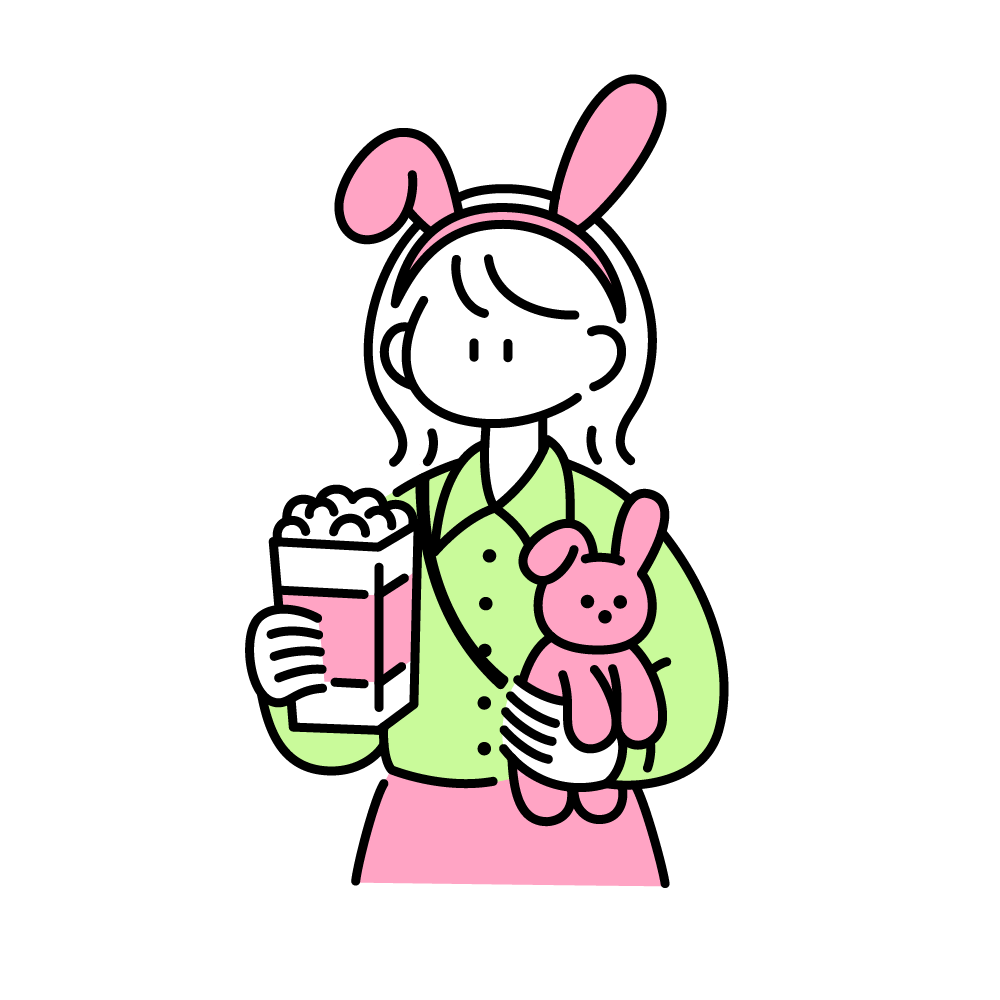
再発はNG
スマホに関する反省文の具体例
以下はスマホ使用に関する反省文の例文です。
この例文を参考に、具体的な内容を追加すると良いでしょう。
私は、○月○日の授業中にスマートフォンを使用してしまいました。
その行為により授業の進行を妨げ、教師やクラスメートに迷惑をかけてしまったことを深く反省しています。 授業中にスマートフォンを使用することは校則違反であり、学びの場である教室の秩序を乱す行為であると痛感しました。
今後はスマートフォンの使用を控え、授業に集中することで信頼を取り戻したいと思います。
皆さんにご迷惑をおかけしてすみませんでした。
また、「スマホ」の部分は他の内容に置き換えて書くことが可能です。
遅刻や忘れ物、友人とのトラブルなど、さまざまな場面で反省文を書く機会があります。
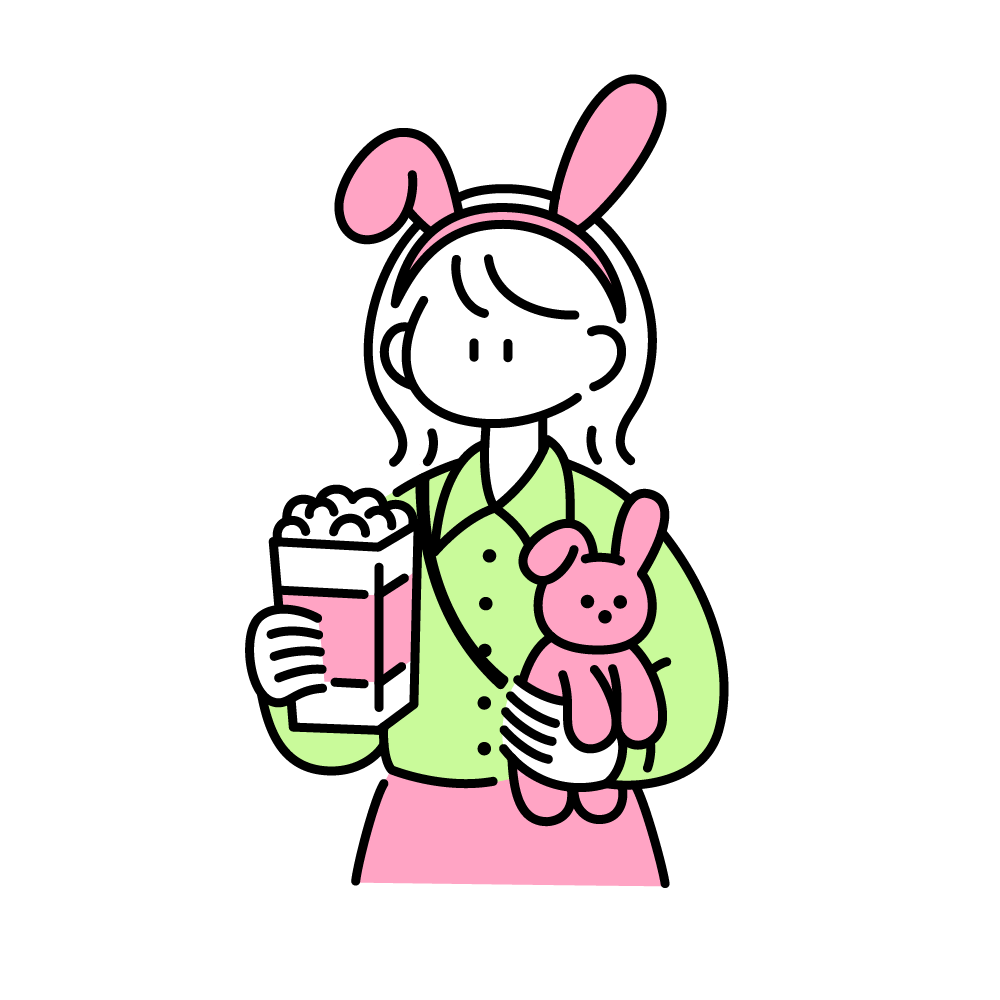
どうしようもない時も正直あるよね
どのような場合でも、基本構成や注意点を守れば、誠意が伝わる文章が書けるでしょう。
なるべく反省文を書かないに越したことはありませんが、書く必要が生じた際には素早く誠実に書き上げましょう。
高校でのスマホ使用に関する反省文で注意するポイント3選
反省文を書く時の注意ポイントです。
この記事では「スマホ使用」に限定していますが、先述の通り、他の事例でも適用されます。
誠実な言葉を使う
反省文では、自分の行動を正当化したり言い訳をしないことが重要です。
例えば、「周りもやっていたから」などの表現は避けましょう。
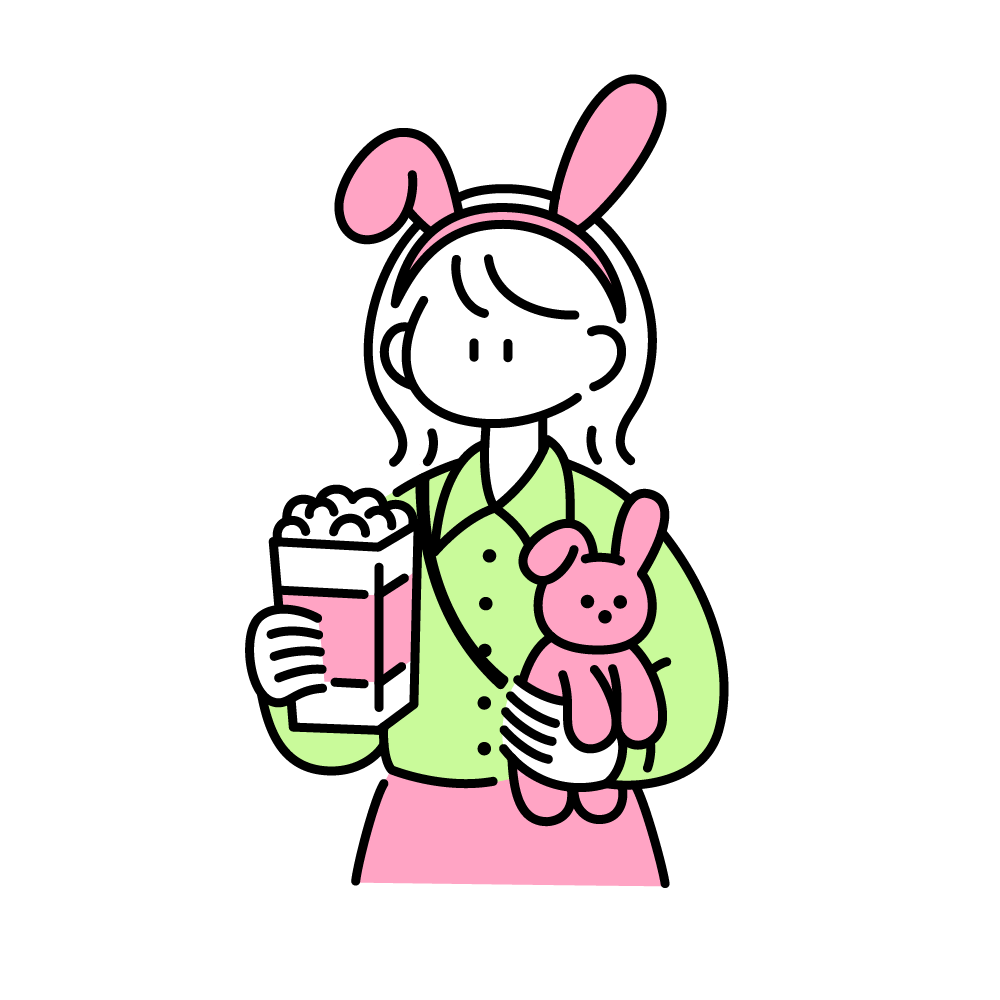
だらしない印象になる
具体的なエピソードを盛り込む
反省文には具体的な出来事や状況を記載することで、誠意が伝わりやすくなります。
漠然とした表現は避け、「○月○日、○時ごろの授業中」と詳細に記述することを心掛けましょう。
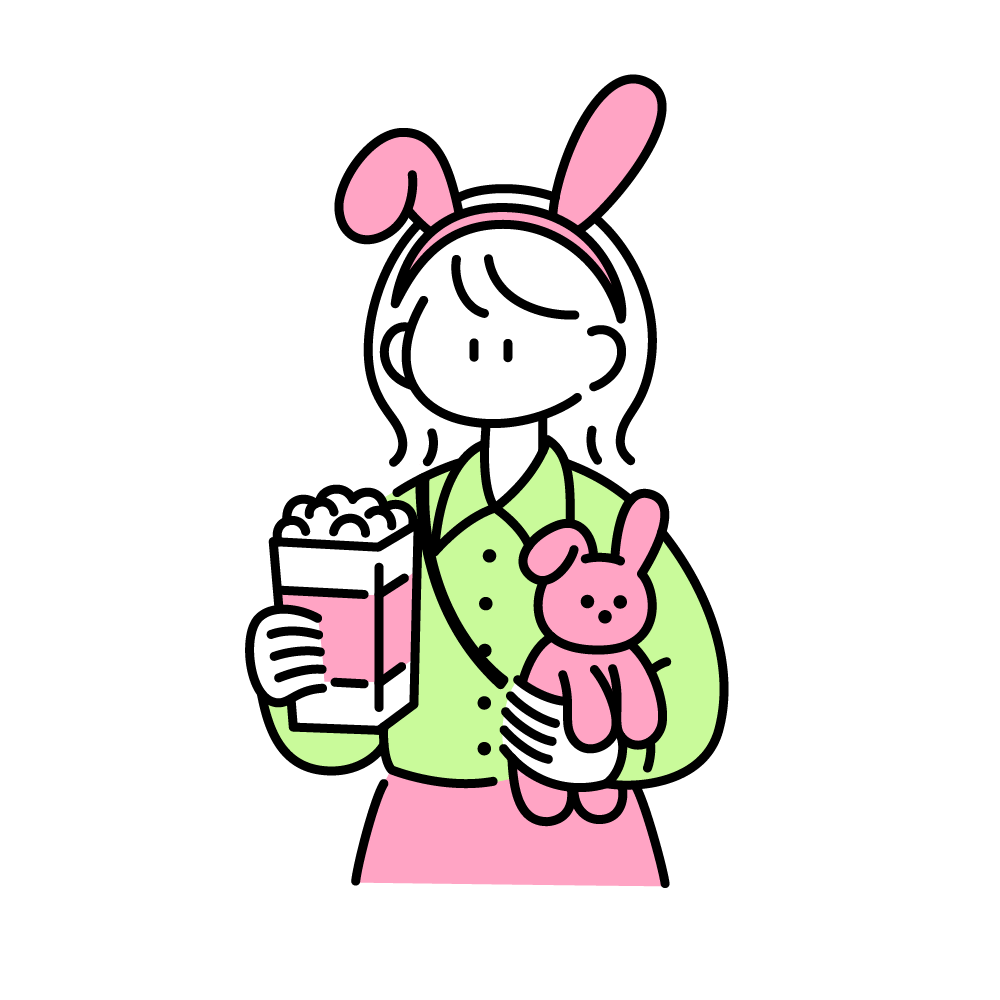
コピペに思われることは避ける
書き手の意志を明確にする
改善策を記載する際は、実現可能な内容を含めることが大切です。
例えば、「スマホを家に置いていく」など現実的な方法を提案するのも一つの手です。
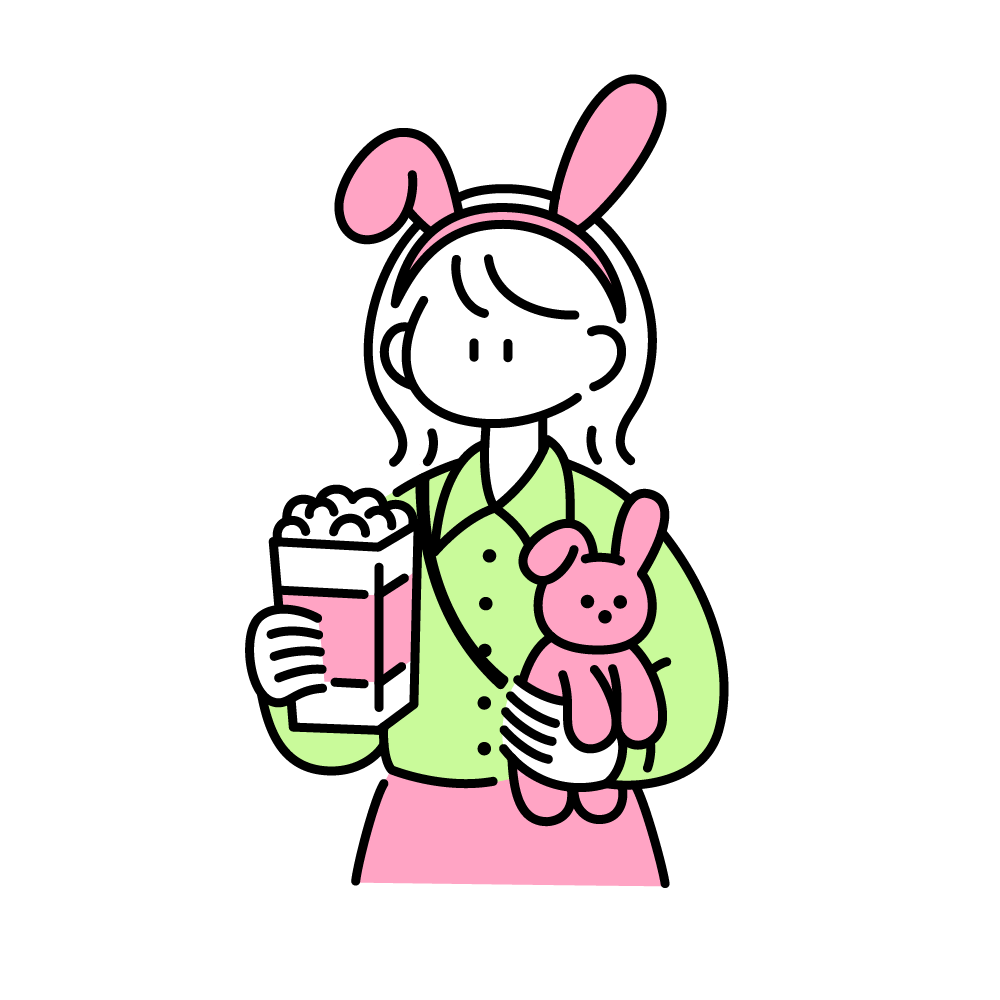
再発防止策は取り組めそうなことを具体的に
反省文を書くときにやってはいけないこと3選
反省文を書く時のタブーを3つご紹介します。
言い訳をしない
言い訳をすると、反省の気持ちが伝わらなくなります。
「少しだけ使ったつもりだった」などの表現は避け、素直に非を認めましょう。
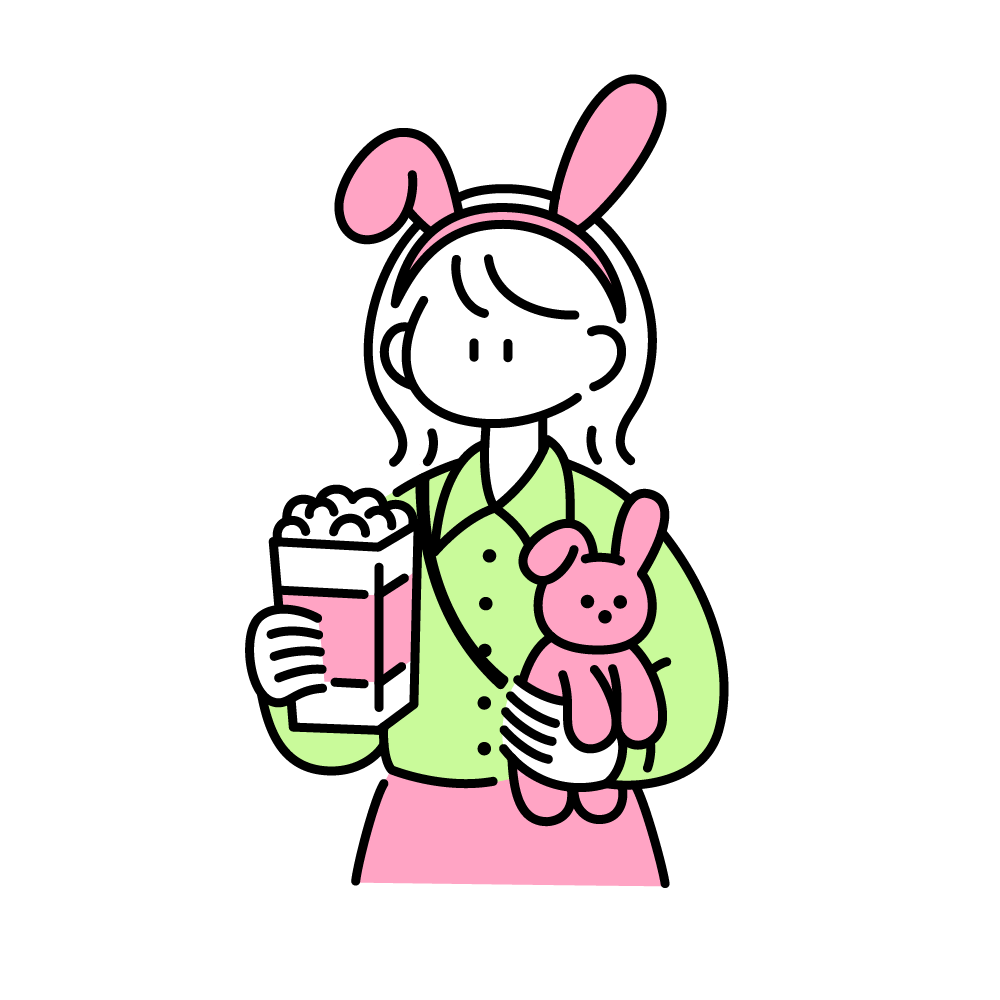
大人も同じでうs
他人の責任にしない
「友人に見せてと言われたから」など、他人を理由に挙げるのは好ましくありません。
自分の行動に対する責任を自覚することが大切です。
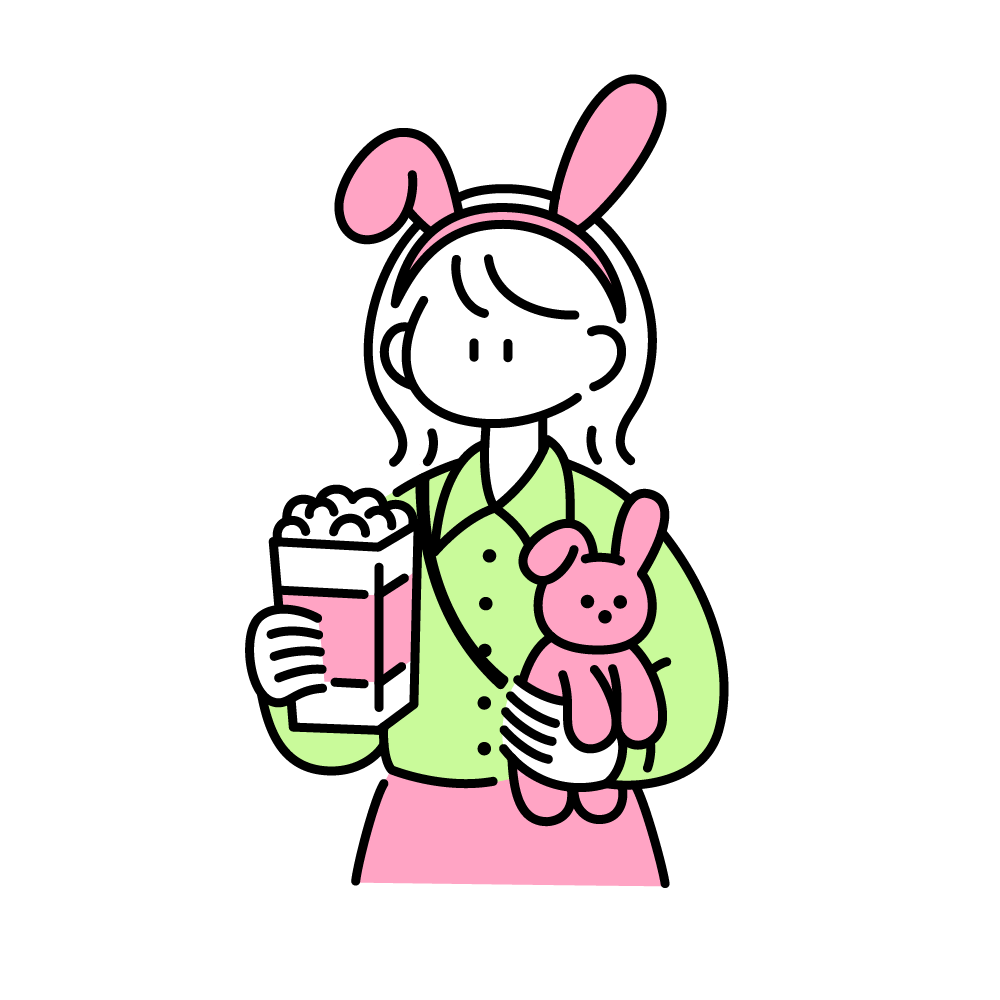
自分の過失は自分で
書きなぐりをしない
反省文は手書きの場合も多く、丁寧な字で書くことが基本です。
急いで書いたり、字が乱雑だと、反省の気持ちが伝わりにくくなります。
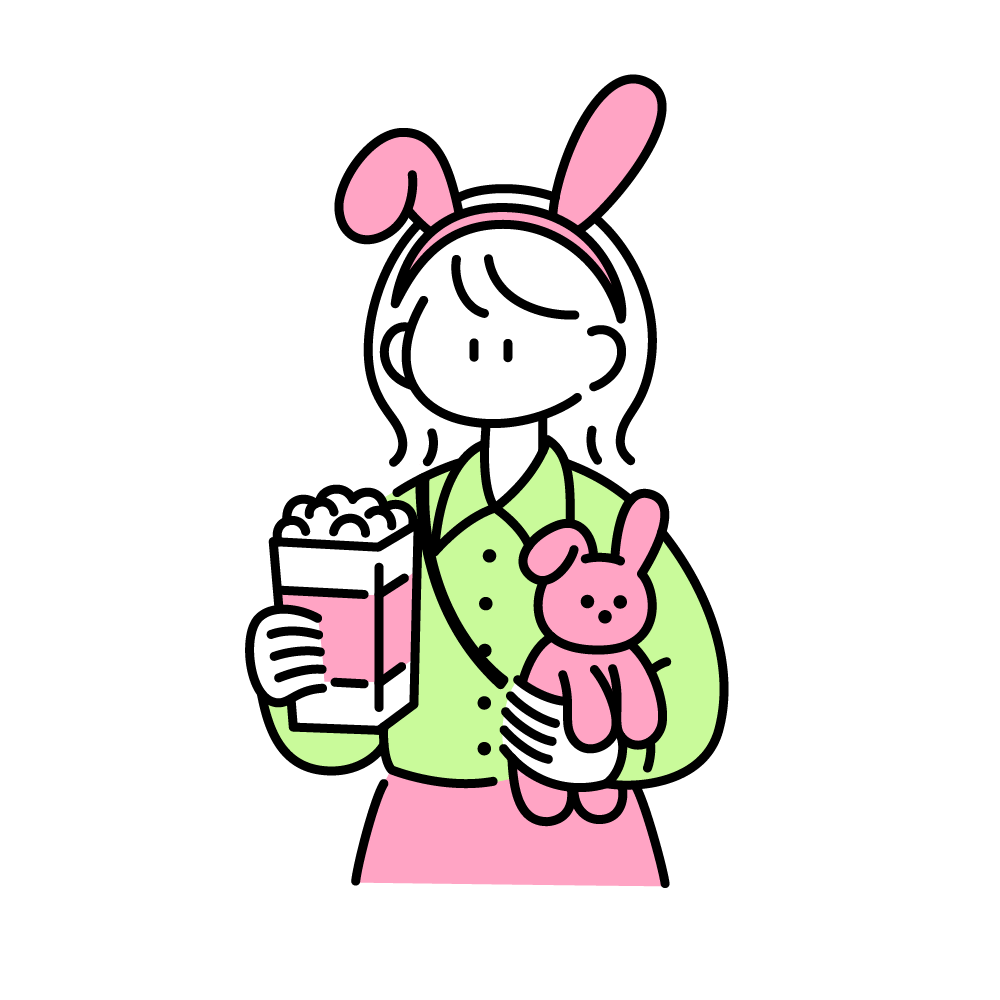
普段の字が汚くても丁寧に書けば伝わります。大人はだませない。
まとめ
高校生がスマホに関する反省文を書く際には、誠実さと具体性が大切です。
状況説明、問題点と反省、改善策の3つをバランス良く盛り込みましょう。
また、反省文を書くことで、自分の行動を振り返り、成長のきっかけにすることができます。
この記事を参考に、真摯な気持ちを持って取り組んでみてください!